※記載している年、所属情報はインタビュー当時のものです。

概要
FFP TFの司会(言語文化研究科博士後期課程)と田尾さん(言語文化研究科博士後期課程)、FFPを修了したばかりの西村さん(言語文化研究科博士後期課程)、村上さん(医学系研究科博士後期課程)、高津さん(人間科学研究科博士前期課程)の5名でFFP修了インタビューを行っています。(所属・学年はインタビュー当時のものです)
前半ではFFPの良かったこと、しんどかったことを語っていただきました。
後半はFFP修了後に焦点を当てるということで、自身の変化・修了できた理由・得た人脈の3つについてお話を聞いていきます。
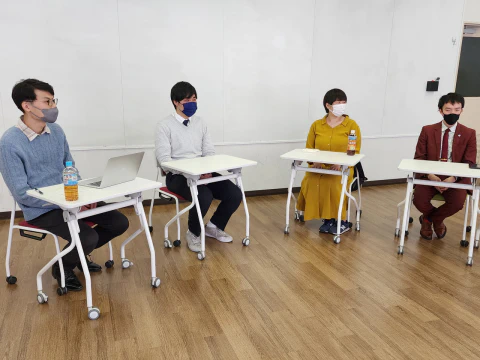
司会:では、後半に入っていきたいと思います。ここからはFFP受講後、ご自身がどういう風に変わったかを伺いたいです。あえて質問はざっくりしているので、ご自由にお答えいただければと思います。例えば、FFPを受けたことで日常が豊かになったとか。
一同:(笑)
司会:どうでしょう、村上さん。
村上さん: 実をいうと、私は看護教育や看護学生教育にめちゃめちゃ興味があったわけではなかったんです。FFP自体はすごい楽しくて充実していたとは申し上げましたが、やっぱり自分は看護師で、自分が看護を研究するとか、誰かに教えるよりは、自分は看護をしたいんだ!って答え合わせしたところがあります。ただ、だからといってFFPを受けなかったらよかったと思ったことはひとかけらもなくて、FFPを受けたからこそ得られた経験もあるし、他分野の人と話して自分の知識が活かすことができたし、卒業も前向きに考えられるようになった。「いつか看護教員になるということも一つの手だな」ということを、FFPのおかげで前向きに考えられるきっかけになったかなと思います。そんなに真面目な意見じゃないんですけど。
司会:実際に大学教員の仕事がどんなんかっていうのを味わわない限り比較もできないですもんね。FFPを受けたことで、自分は看護師なんだって再確認できたんですね。
村上さん:あと貴重だったのが、FFPを受けている人たちって、大学教員になりたいという人が多いじゃないですか。そういう人たちと話すことで、いい意味で自分の研究に対してまじめで、前向きなところを見れたのが刺激になってよかったなと思いました。
司会:なるほど、やっぱり他の人の話を聞くことが自分に返ってきたということですね。
村上さん:そうですね。正直期待していたよりも、自分に返ってきてその後に反映されてるなと思いました。
司会:うんうん、なるほどありがとうございます。
司会:西村さんいかがでしょうか?
西村さん:授業で、ロボット工学の義足の話とかしている同級生と出会ったんですけど、この話は授業終わっても教えてほしい、聞かしてほしい!みたいな感じで。
司会:なるほどなるほど。
西村さん:色んな分野に対する恐怖心がなくなっていった。特に、私根っからの文系ですので、理系とかまったくだめだったんですけど、「あ、これは研究の結末が気になるなみたいな」のがありました。自分自身のアンテナが広くなったというのがあります。
司会:なるほど。
西村さん:あと教育というものがこれだけ面白いものだということに気が付いてしまいました。日本教育工学会での発表は続けられる限りは続けられればと思っています。いっときは、指導教員から「博論のテーマを変える?教育の話にする?」という話がでるくらいで(笑)。頭の半分以上は教育に関する興味がある状態です。
一同:(笑)
司会:教育工学ってオープンな学問ですよね。僕いまから医者とか看護師になろうとしても無理ですけど、教育工学はアカデミアに残る人全員に関係すると言ってもいいと思います。FFPを受けていなければ、西村さんはそこまで興味持つに至らなかったですよね。
西村さん:至らなかったと思います。ある意味、FFPの延長みたいな感じで、全然違う分野でも学べるというのは、幸せで胸いっぱいです。
一同:(笑)
司会:さあ、高津君はどうですか?
高津さん:そうですね、先ほど開発論IIIの話でもあったんですけど。研究の動機についてのレポートはM2で博論のことが決まっていない中でエイヤってだしたんですが、それでも授業で書いたことで、「そういうところにかっこよくかける研究がしたいな」って思うようになりました。教育の視点でいくと、IIで1回授業したんで、自信が持てたなって思います。
一同:おー!
高津さん:1回だけなんですけど、はじめの1回は大きいと思うんです。30-40名くらいですかね、大教室で自分の専門のことを教えた経験は、自信になったんで。目に見えない変化ですけど、その2つがあるなって感じです。
司会: FFPでの初めの1回目というのは大きな経験になるでしょうね。
司会:さあ、田尾さんどうでしょう?
田尾さん:教育面でももちろんあると思いますが、どっちかと言えば僕は研究の方かなと思います。FFPを受けた後、研究の話をしたり聞いたりするときに思うようになったことがあって。それは何かというと、「研究のための研究」をしているというか、社会の何の役に立つの?とか、誰のための研究なの?ということにうまく答えられているのかなと。「自分の中で、これが唯一解でめちゃめちゃ面白いものだから、これを追究するんだ」っていうスタンスでもいいんですけど、そうであれば自分の研究の面白さを端的に伝えられるようにならないとって僕は思います。
司会:確かにそうですね。
田尾さん:FFPでは、異分野の人や学生に自分の研究について話す機会がたくさんあって、自分がやっていることをかみ砕いて、興味深く、面白く見せなきゃいけないんです。自分の研究をわかりやすく面白く伝えるということは、教育だけじゃなく、研究者としても大切なことだと思います。
司会:なるほど。FFPを経ないと、そういう考えには至らなかった?
田尾さん:経ないと、というか、FFPを受けてたくさんの人と話したからこそ気づいたことだと思います。なので、それをする機会があるというのが大きいところ。先ほど、色んな分野の人が集まると言いましたけど、FFPならではのメリットがそこにあると思います。
村上さん:人文に限らず、看護でも、あんなに人と関わる仕事をしてるのに、学生に教える・部下に教えるとなると、正直そこの能力はあんまりかなって人はいます。
司会:FFPで学ぶメリットは大学教員になるだけではないということですよね。例えば、企業に就職したとしても、社内研修で後輩に教えるとか、どんなキャリアを歩んだとしてもあり得る状況だと思うので、大学教員になるためとか、研究者として生きるためのメリットだけでなくて、本当に生きる糧として、大事なことを学べる場でもあるんかなと思える次第です。

司会:さあ、ところで皆さん、FFPIのあとが続かないという人がそれなりにいるんです。そのなかで、皆さんは修了されたわけですよね。それはぶっちゃけなんででしょうか? 何が動機となって、I, II, IIIと修了できたのかっていうのを聞いてもいいですか?
村上さん:はい、私はFFPIを受けた時に、「あ、思ったよりも誰でも授業ってものはやろうと思えばできるんだ」っていう感覚を味わえました。なので、それを味わえたからこそ、大変だよって聞かされていたけど、この環境やったらそんなことないんとちゃうかなと思って、後期でIIとIIIを迷わず登録させていただきました。I,II,IIIを順に受ける中で、色んな先生方だったり、TFさんだったり、他の受講生と関われる機会が、前向きに取り組めたポイントだったんかなと思います。
司会:なるほど、なるほど。西村さんは?
西村さん:大学教員を目指す以上は履歴書にかけるものが必要だと思っていましたし、私は最後までやらないと気が済まないので、IIIまで絶対完結させるぞって思って。あとIを受けた時に、佐藤先生や浦田先生を見て、これはすごいものだ、この人たちがやっている大学教員養成というのは大事だと思いました。
一同:(笑)
司会:さあ、高津さんは修論と一緒にやって忙しかったけど、どうでしたか。
高津さん:僕の分野が教育工学研究室で、しかも高等教育に近いことをやってるんです。FFPIを受けた日から、自分はこの研究をしてて博士課程に行くんやったら、この科目は必須科目やなって思いました。
司会:ちなみにお三方に聞きますが、Iの後にこの感じやったらいけるなって思う何かがあったってことですか?
全員:そうですね。
西村さん:先生方の真剣さがすごいなって思いました。本当に先生方の授業や対応がすごくて、これは絶対光るものがあるなって感じで。自分は自分の専門以外の授業で、一般教養とか全然真面目に受けていないんですけど、初めて自分の専門外でここまで一生懸命になれた授業でした。
村上さん:たしかに。
高津さん:僕にとっては、専門教育として受けているというのがありました。
司会:皆さん、最初から全て取るつもりでいたから修了できたというのはあるかもしれませんが、TFの田尾さんとしては、やはり皆さんに修了してほしいという思いでしょうか。
田尾さん:やっぱり現実問題、研究とか他のことが重なって忙しい、難しいというのはもちろんあると思います。概論的なIを受けて十分だって思えたら、Iだけでもすごく勉強になるので、それはそれで良いと思います。その一方で、Iで基本的な部分を学んで、「もっとやりたい、せっかく学んだことを活かしたい」って思ったら、II, IIIでしか得られない実践経験や学びもあるので、ぜひ受講してほしいですね。
司会:ちなみに、副プロの修了証が出るっていうのはモチベーションになりましたか?
一同:なりました。
村上さん:なりました。今日持ってきたくらいです。
一同:(笑)
高津さん:嬉しかったです。学位記と一緒にもらったんですけど、嬉しいですよね。
村上さん:「IIはハードル高いって聞くからIで終わるわ」とか、「難しそうやからIとIIIだけにしとくわ」って言う研究室の先輩後輩もちらほらいました。
司会:それで、さっきからIIはそんなにハードル高くないぞ、そこまで心配せんでいいぞってくりかえし仰っている(笑)。
村上さん:そうです、でも周りには全然信じてもらえないです(笑)
司会:まあ、3つやってこそ見える景色があって、それをここにいる全員が共有しているような感じがしますよね。

司会:では、続きまして、他の研究科の人と学ぶメリットが出てきていたと思うのですが、FFPを通して新しい人脈は得られたか、聞いていきたいと思います。まず西村さんからいきましょうか。
西村さん:まず受講生同士でも、お互いの研究の話で盛り上がりました。あとはFFPで出会った先生のご縁もあり、先日は日本教育工学会で発表してきました。FFPの人脈で研究がかなり進められそうです。
司会:これからが楽しみですね。さあ、村上さん。
村上さん:私は特に人脈に期待して受講したわけではなかったんすけど、何でかある人文学系の方ととても仲良くなったから、儲けものやなって思います(笑)
一同:(笑)
村上さん:私は、もう博士課程になっていまさら友達はええかって思ってた。だから、意図せずしてできた友達って、すごいお互い惹かれるものがあったからこそ今に至ると思うので、この縁は大事にできたらいいなと思います。また、出会った先生や受講生とも何かのきっかけで再会できたらいいなと思います。
司会:そうですよね。高津さん、人脈どうですか?
高津さん:僕は、研究室以外での先輩ができたというのがありますね。来年から僕もさせてもらうんですけど、TFの方と繋がることも多かったです。僕は前期課程なんで可愛がってもらってます(笑)。
司会:情報提供しておくと、FFPのOBOGの集まりで阪大若手FD研究会というのがあって、FFPの修了生が繋がる場が用意されています。FFPが開講されて10年近くになりますので、僕たち院生の一歩あるいは二歩先を進んでいる先輩と繋がる場を提供できるようになってきたんやなと思います。
必修科目「大学授業開発論Ⅰ」を受講したい方は、期日までに、KOANにて①副プログラム「未来の大学教員養成プログラム」の申請、 ②「大学授業開発論Ⅰ」の履修登録をしてください。 授業実施2週間前ごろに、履修登録者に事前課題等のご連絡をします。 *大阪大学の副プログラムに関する説明や申請方法、履修登録・修正期間の案内はこちらをご確認ください。 *2022年度からウェブエントリーならびに選考がなくなりました。必ず上記の①②を済ませてください。